1.目覚め
♪♪♪…
当面できることもなく、また気力も生じなかったので定時に事務所を出て帰宅した私に、待ちかねた電話が来た。
「玉澤宙です。狩野さん、父が先ほど目覚めました」
「本当ですか。話はできますか。記憶はありますか」
「どちらも大丈夫です。お医者さんも、まだしばらく検査や様子見は必要だけど、大きな異常も後遺症もなさそうだって」
「ありがとうございます。すぐ、向かいます」
部屋から駆け出して外へ出た私は、駐車場のバイクを見やったが、思い直して下北沢の駅に向かった。一瞬でも早く会いたいが、もう焦って無理をする必要はない。

新宿に向かう小田急線の車窓には夕焼け空が広がっている。窓の方を向いた私の目からぽろぽろと涙が頬を伝う。まわりの人は、夕陽の美しさに感動している何と純真な乙女かと思っているかも知れない。私の目に夕陽は見えてはいるが、私は夕陽など見ていない。
この5日間、止めどもなく、まさしく私の人生での記録を何度も塗り替えて流し続けた悲しみの涙ではない。打ちひしがれて流した涙とは違い、悲しみを感じていないのに流れ落ちる涙は、私の心を洗ってくれる気がした。
病院に着いた私を宙さんが迎え、私たちは駆け寄ってハグをしあった。
「よかった…」
「父が助かったのは狩野さんのおかげです。本当にありがとうございます。早く、父に会ってあげてください」
宙さんに手を引かれ、私たちは病院の階段を駆け上がり、病室に向かった。
病室のスライド式のドアを開けると、玉澤先生がベッドの上で起き上がり、医師と話している姿が目に入る。
「今夜はゆっくり眠ってください。ずっと眠っていたとはいえ、体は回復のためにまだ休養を求めていますから。面会の方も、そのつもりで」
医師は私たちに目配せして、出て行った。
「たっちゃん、狩野さんが来てくれたよ」
(たっちゃんって…)
「あぁ、ありがとう。迷惑をかけてしまったね。仕事こなすのたいへんだったろう」
「あぁ、あぁ…」
私は、こみ上げてくるさまざまな感情の渦に飲み込まれて言葉を発することもできず、その場にへたり込みそうになるのをようやく耐えて踏みとどまっていた。
「じゃあ、私はいったんうちに帰ります。たっちゃん、また明日の朝来るから」
「あぁ、ありがとう。宙ちゃんもゆっくり寝てくれ。ずっと眠れなかったんだろ」
「うん、今夜はしっかり寝るよ。じゃぁね」
宙さんが病室を出て、私は玉澤先生と2人になり、立ち尽くしたまま、何とか思いを言葉にしようともがいていた。
「こんばんは。玉澤さん、意識が回復したって?」
宙さんと入れ違いに、素太刑事が病室に入ってきた。
「離してよ。私が犯人なはずないでしょ」
「まだそういうわけにはいかないんだ。あんたは現時点では重要参考人だ」
後方で、六条さんと祟木刑事が言い争う声が聞こえてくる。
「やぁ、狩野さんか、いいところをお邪魔しちゃったかな。すぐ失礼しますから許してください。玉澤さん、新宿警察署の捜査1課の刑事、素太伐実です。目が覚めたばかりで体調もよろしくないと思います。詳しいお話は後日聞かせていただきますが、今、一つだけ確認させてください」
「はい」
玉澤先生が怪訝そうな顔で応じた。
「襲われたとき、犯人の顔を見ましたか」
「残念ながら、犯人は目出し帽をかぶっていたので、顔は見えませんでした」
素太刑事はあからさまに落胆した様子を見せた。
「残念だな、嫌疑は晴れなかった」
祟木刑事が部屋の外で六条さんに冷たく通告している。
「えっ、六条さんを犯人だと疑っているんですか?それはないでしょう」
やりとりを耳にした玉澤先生が素太刑事に話しかける。
「どうしてわかります?」
「顔は見えませんでしたが、最初に『玉澤さん』と声をかけられました。その声は男の声でした」
「そうですか」
素太刑事はため息をつき、祟木刑事に、もうリリースしていいと伝え、また明日来ると言って帰っていった。
2.爆発
素太刑事が立ち去ると、六条さんが病室に駆け込んできた。
「玉澤くん…」
六条さんは、しばし入り口で立ち止まり、玉澤先生の様子を見、私を横目で見て牽制した後、私の横をすり抜けてベッドに駆け寄った。
「バカバカバカ、私がどんなに心配したか」
六条さんは、ベッドの上で上体を起こしている玉澤先生の胸に飛び込み、次いで玉澤先生の背中に腕を回し、抱きしめた。
私は、せっかくの2人きりのチャンスを逃し、後からやってきた六条さんに先を越され、つくづく自分の行動力のなさ、出足の悪さ、ためらいと、六条さんの思い切りのよさ、瞬発力を引き比べ、嘆きつつも呆然としていた。私も、ああしてみたい。いや、しかし私は、これまでも六条さんと我が身を比べ、六条さんと違って、私が同じことをしても似合わないと引き下がってきた。今回、六条さんの邪魔が入らなかったとして、私は、ああいうふうにできただろうか…
「みっちゃん、心配させてごめん。でも、もう大丈夫だよ。みっちゃんが望んだようにたっぷり休んだよ」
「私は、こんな休み方望んでない。大けがして体力をすごく消耗してるのよ。これくらいじゃ休んだことにもならない」
六条さんは顔を上げて玉澤先生を睨んだ。
「私、玉澤くんが死んじゃうかも知れないって、そう思ったら、私、私…」
「みっちゃん、ごめん」
「それなのに、こんな時にまるで冗談みたいなこと…」
六条さんはぽろぽろと涙を流し、玉澤先生の顔を正面から見つめた。
「もう、これ以上しゃべらせない」
「みっちゃ…」
六条さんは、玉澤先生をにらみつけながら、驚きの表情の玉澤先生の口を、唇で塞いだ。眼前に迫った六条さんの目線の勢いに負けて玉澤先生が目を閉じた。六条さんはそこでようやく目を閉じて、玉澤先生の唇を味わうように濃厚なキスを続け、右手を玉澤先生の首筋から後頭部に当て、左腕を玉澤先生の背中にしっかりと回して胸を合わせて抱きしめた。私には永遠に思える時間、実際にも2分か3分は続いたかも知れないが、2人は1つになっていた。
そして六条さんは、その後黙って病室を走り去った。後にはあっけにとられた私と、やはり呆然とした玉澤先生が残された。
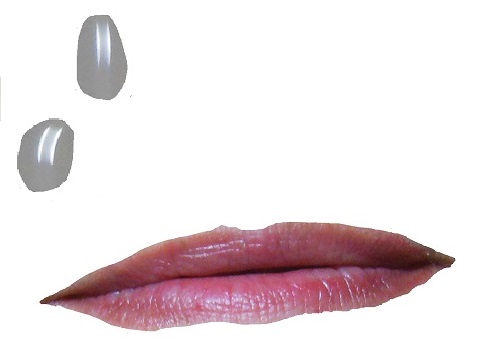
3.抱擁
六条さんの暴走に毒気を抜かれた私は、ようやく金縛りが解けたように、玉澤先生の方に歩み寄ることができた。
「みっちゃ、いや、六条さんに、何か悪いこと言ったかな」
「六条さんも、先生のことが心配で夜も寝られなかったし、さっきも言っていたように先生がこのまま目を覚まさなかったらと思うと、そう考えるだけでそのままうずくまって泣きじゃくりたくなるような、そんな日々を送ってきたんです。そこへ、今日は、先生を襲った犯人扱いされて警察で厳しい取調を受けていたんです。私も昨日までそういう立場にありましたからよくわかりますけど、どうにも抑えきれない悲しみや怒りやどう呼んでいいやらわからない感情で身もだえする思いだったんだと思います。そこに先生が助かったという安堵感はあったけどそれも含めて感情的にもみくちゃにされて不安定になっているところに、先生には悪気はなかったと思いますけど、六条さんの思いからすれば報われないような不用意な言葉があって、それをきっかけに爆発したんだと思います」
それだけじゃなくて、先生の心を私の方が掴んでいると六条さんに思わせていることから来る焦りや、今日は私までもが六条さんを疑う態度を取っていたことへの怒りも、六条さんの爆発の大きな誘因となっていると思うが、それは黙っておこう。先生の覚醒が六条さんの爆発の引き金になったということにしておいた方がわかりやすく安全だ。私との競争心からのフライイングボディアタックが第1の爆発、不発に終わった先日の告白が第2の爆発とすると、第3の爆発、サードインパクトは、先生の覚醒がトリガーになったと。
「先生、だからさっきのことで、六条さんを責めないであげてください。六条さんはいっぱいいっぱいだったと思います」
「みっちゃんを責める?」
「全然咎める気がないって言われると、私が傷つくんですけど」
玉澤先生の口元が警戒心でこわばるのが見える。六条さんに不用意な発言をして感情を爆発された後だけに、私にまた不用意な発言をしては、と気にしているのだ。相変わらず女心には鈍感な玉澤先生だが、私はその初心さも好んでいるし、それを利用して操縦する気になれば、思いのほかたやすく見える。六条さんは、こうして玉澤先生を手玉に取ってきたのだろう。でも、今は私の時間だ。
「一方的に唇を奪われたんですよ。うるさく言えば犯罪にもなりかねない。見ている前で愛する人の唇を奪われて、私の心は痛く傷つきました」
「そうだな、済まない」
「ん~、先生に謝られるとますます腹立たしいんですけど。私が言いたいのは、六条さんがしたことはよくないことだけど、でも六条さんが追い詰められて精神的にギリギリの状態だったことは、私もよくわかる。だから、六条さんを責めないで、今度会ったときも何もなかったように、これまでどおりに接してあげて欲しいっていうことなんです」
「わかった」
「先生、六条さんだけじゃなくて、私も、心配してました」
玉澤先生の傍らに立った私は、玉澤先生を抱き寄せ、玉澤先生の顔を私の胸に押しつけて包み込んだ。
「心配かけて済まない」
「先生が謝ることないですよ。先生は被害者です。私は、先生のことが好きで好きでしょうがなくて、今回、改めてそれを再認識しましたよ。先生がもう目を覚まさないかも、と考えただけで胸が潰れそうになりました。私はそのことを先生に受け止めておいて欲しいだけです。私がこういうことするの、似合わないと自覚してるんですけど、今回何度も悲しみで満たされたこの胸を、もう一度、先生への思いと安心と幸せでいっぱいにしたいんです。しばらくこうさせてください」
「ありがとう」
「先生、頭の傷、痛みますか」
「少しね。それほどじゃあない」
「ちょっと見てもいいですか」
「あぁ、いいよ」
私は玉澤先生の頭の包帯を外し、頭頂部の傷跡を目の当たりにした。もう出血はしていないが、縫い目が痛々しい。玉澤先生に、こんなけがをさせたヤツを私は許さない。私は玉澤先生の頭を抱きしめて自分の胸に押しつけたまま、頭頂部の傷跡に唇をつけ、慈しむように頭をなでた。
4.約束
しばらく、もし六条さんが見ていたら、我慢できなくなって卒倒するであろうくらい長い時間、玉澤先生を抱きしめて堪能した後、私はベッドに腰を下ろし玉澤先生と並んで座った。サイドボード上に、外されたままのバイタルサインの測定・発信器が置かれているのを目にして、私は、話さなければならないことがあるのを思い出した。
「先生、私、先生を騙してました」
「それのことかい?」
私の視線の先を見て、玉澤先生が尋ねた。
「ええ、それは時計じゃなくて、バイタルサイン、脈拍や呼吸数、体温なんかをGPSデータとともに私のスマホに送信する機械です。時計の機能と外観はありますが」
「さっき、お医者さんから聞いたよ。でも、それをつけていたからこそ襲撃されたことが狩野さんにわかって、狩野さんが駆けつけてくれたおかげで私は今生きていられるというわけだ。それに、狩野さんは私にこれが『時計だ』とはひと言も言わなかった」
「それは官僚がよくやる詭弁で、私は確かに時計だと積極的には言いませんでしたが、先生が時計だと受け取るように仕向けました」
「官僚だけじゃなくて、弁護士も守秘義務や依頼者に対する誠実義務と真実義務に挟まれてよくやることさ。そのレベルのことを非難してたら弁護士業務はできないよ。狩野さんは嘘はついていない。胸を張ってそう言うべきだ」
「仕事上の作法と、愛する人への誠意はレベルが違うと思いますけど」
「それ、取ってくれる?」
玉澤先生は、私からバイタルサインの測定・発信器を受け取り、左手首にはめた。私のスマホにデータが動き始めたことを示す表示が復活した。私はそっと玉澤先生に体を寄せて、そのスマホの画面を見せながら聞いた。
「先生は、私に、こんなふうに体のデータと居場所を把握されるの、いやじゃないですか」
「いや、かまわないよ。ずっとつけてるって約束したんだし」
私と玉澤先生のホットラインは、今、本当の意味でつながった。
「ところで、先生」
私は、微妙に体をよじって玉澤先生の肩に背をつけ少しうつむき加減になり、玉澤先生の顔を見ないで言った。
「さっきの、襲撃される前に『玉澤さん』と呼びかけられた、それが男の声だったって話、本当ですか?どこがっていうわけじゃないんですけど、その時の先生の表情、いつになく不自然で…」
「狩野さんには見破られたかな。嘘だよ。何も言われずにいきなり殴られた」
「六条さんをかばうために、とっさに嘘をついたんですか。だとすると、犯人が六条さんじゃないとは言いきれないということになるんでしょうか?」
「それはないよ。いくら目出し帽をかぶって顔がわからなくても、六条さんや、狩野さんなら見間違うことはない。犯人は別人だ」
「自信を持って、そう言えますか?」
「あぁ。それに、犯人の目星はついている」
第16章 逆転 に続く
この作品は、フィクションであり、実在する人物・団体・事件とは関係ありません。
写真は、イメージカットであり、本文とは関係ありません。
この作品のトップページ(目次ページ)に戻る ↓
「小説」トップに戻る ↓
他の項目へのリンク